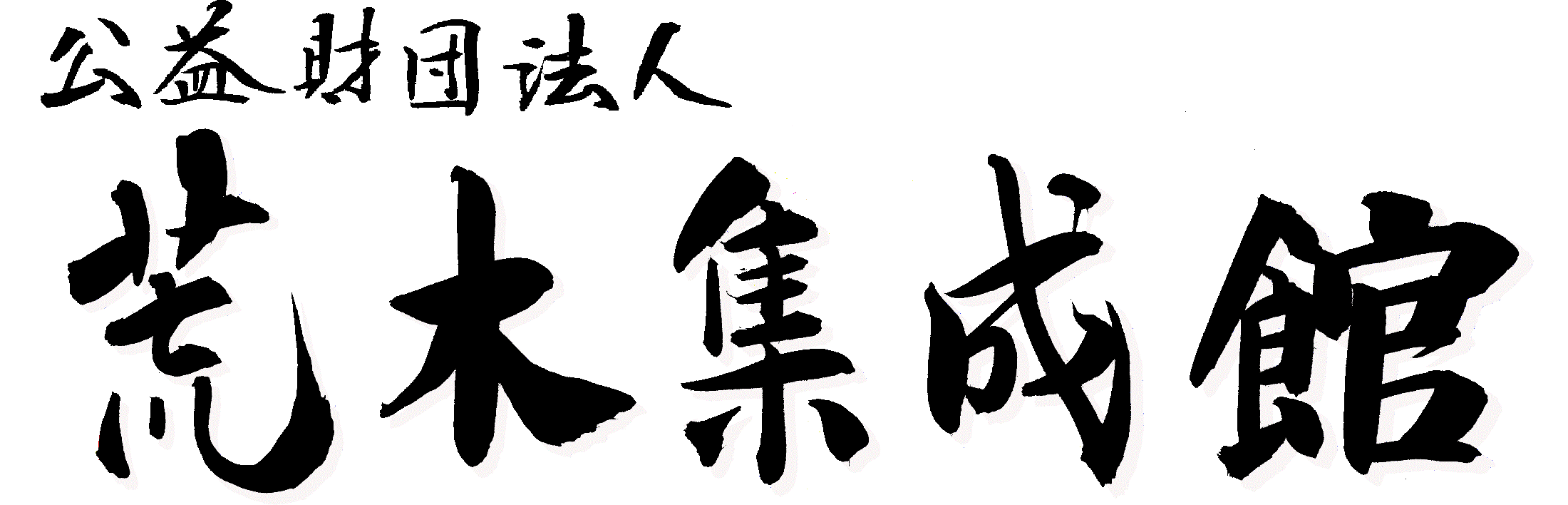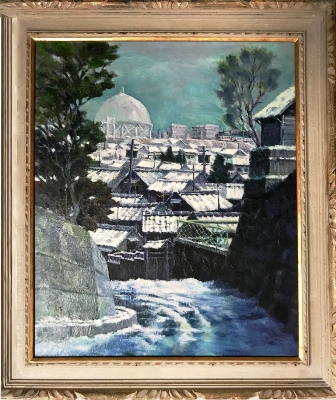| Araki Syuseikan Museum | 〒468-0014 名古屋市天白区中平5-616 |
Home >
荒木集成館所蔵品名古屋のやきもの101
学芸員実習生による展示
令和7年5月10日(土)〜8月3日(日)
正木焼とは
尾張藩の藩士である正木惣三郎・伊織親子の作である。父の惣三郎は藩に仕える傍ら、余暇には主に器を制作し、子の伊織も同じく藩士として仕え、余暇には緻密な香合や置物を制作した。
豊楽焼とは
愛知県名古屋市中区大須の万松寺南にて、1708年から初代利慶、二代豊八、三代豊助、以降も連綿と続き、大正時代まで約130年間焼き継がれた陶器である。草花木石の絵付けと緑を流しかけたデザインが特徴で、作品の種類も豊富である。三代以降は豊助名を名乗っていたため、何代の作品かを判別するのは困難である。
学生展示について
愛知淑徳大学から学生2名で今回の展示を行いました。講義で学んだことを活かして、実習生として初の展示に挑めたことを嬉しく思っております。今回の展示は荒木集成館所蔵品の展示ということで、尾張藩、ひいては愛知県にゆかりのある焼き物を101点展示いたしました。運搬作業や展示作業だけでなく、パンフレット、看板、キャプションに至るまで全て学生で製作し、展示を行うという貴重な体験をさせていただけたこと、そしてこの展示を通して学んだ展示製作の楽しさ、難しさ、全てを胸に今後も励んでいこうと思います。
学生の渾身の展示、最後まで楽しんでいただけたら幸いです。
荒木集成館の概要 〜地元の歴史・文化がわかるコレクション館〜
|
荒木集成館は、集成館という名があらわすように、考古を中心としたあらゆる収集品(コレクション)を展示・紹介する博物館です。 1952(昭和27年)、中学教師だった荒木實は、生徒の拾った一片の土器をきっかけに考古学の研究をはじめました。そして多くの遺跡の発掘調査に参加し研究を続け、1970(昭和45)年10月31日、名古屋市千種区に自らの力でミニ博物館「荒木集成館」を設立しました。 その後、1978(昭和53)年12月14日、天白区に財団法人荒木集成館として移転。そして平成25年12月3日付けで荒木集成館は「財団法人」から「公益財団法人」になりました。 二階の常設展示室では、土器や石器などの考古資料を時代ごとに展示しています。特に荒木自身が発掘・調査研究を行ってきた「東山古窯址群」と呼ばれている昭和区・千種区・天白区の遺跡からの出土品が、展示の中核となっています。 一階の展示室では、化石・陶磁器などジャンルを問わず、さまざまな展示会が行われています。ここは、一般の収集家や研究者の方々の長年の成果を発表する場となっています。当館が収蔵する江戸時代から昭和にかけて数多く焼かれていた名古屋のやきもの展示も定期的に行っています。 |
X(旧Twitter)※最新情報はXから直接ご確認ください
特別展示のご案内
— 荒木集成館 (@arakishuseikan) May 2, 2025
荒木集成館所蔵品展
「名古屋のやきもの 1〜101」
江戸時代から昭和初期にかけて名古屋で生まれた、多彩なやきものの世界をご紹介いたします。
職人の技と美意識が息づく逸品の数々を、ご鑑賞ください。
令和7年5月10日〜8月3日
皆さまのご来場を心よりお待ちしております。 pic.twitter.com/fKClBs10kE